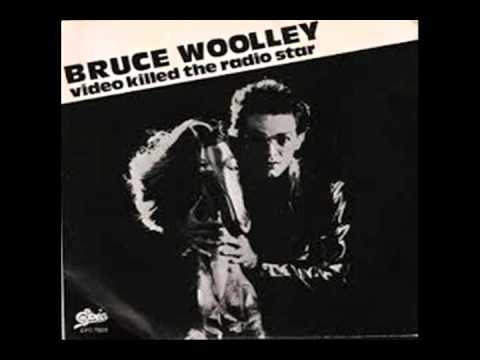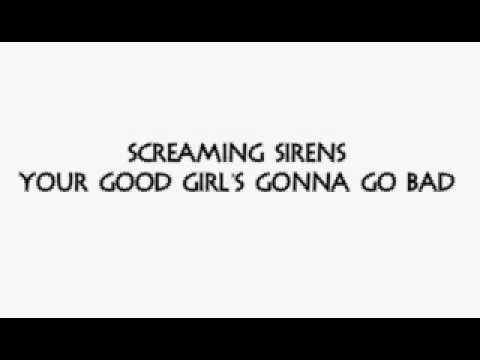【今回はひねりのない直球。扉絵もシンプルに手抜き】
【今回はひねりのない直球。扉絵もシンプルに手抜き】
ROCKHURRAH WROTE:
ROCKHURRAHが勝手に「過去の企画、再発掘」というような感じで、ピッタリと途絶えてしまったシリーズ記事を再び書こうとしているのは本人以外誰も気にも留めてない事と思う。
この「誰がCOVERやねん」のシリーズも1年くらいは書いてないなあ。
ブログ自体をそんなに書いてないから時の経つのもあっという間だよ。
最近はなぜかとても忙しくて、週末に頭を使う気力さえ出てこない始末。
もっとゆったり出来る時間があれば少しは何か出てくるのかも知れないが、本人の気質とは裏腹にあくせく毎日駆けずり回ってる。
さて、今回のテーマは特に決めてないけど、それでよろしいか?
この企画の当初は単に目に止まったカヴァー・ヴァージョンの曲を羅列して簡単なコメントを書くだけというシンプルなものだった。
しかし3回目くらいから飽きてきて少し趣向を凝らすようになったのが敗因。
色んな括りに自分でがんじがらめになってしまい、書くのが非常に難しくなってしまったのだ。
週末に頭を使う気力さえ出てこないのに難しいのは困る。
元来、ひねりすぎの傾向にあるROCKHURRAH、今日は久々に直球で行かせてもらおう。
曲も割とシンプルなのを選んだよ。
ちなみに今はじめて当ブログを読み始めた人にはわからないだろうが、ずっといつまでも70〜80年代のパンク、ニュー・ウェイブがメインの記事を書いてるから選曲見て「いつの時代?」とか思わないように。
Ca Plane Pour Moi / Sonic Youth
この曲は色んなところで使われているから知ってる人も多かろうが、ベルギーの70年代パンク・バンド、プラスティック・ベルトランがオリジナルだ。
元々はハブル・バブルというポップなパンク・バンドだったがプラスティック・ベルトラン名義のこの曲が奇跡の大ヒット。
ROCKHURRAHのブログでも何回も書き続けているね。
例えばパンクの代名詞、セックス・ピストルズやクラッシュやダムドなんかが、遊んでても超自然的な力で勝手にメジャーになったとは誰も思わない。目に見えないところで作曲者も演奏者も歌い手も何らかの努力はしてるのが当たり前だろう。
このプラスティック・ベルトランももちろん、どこか陰で努力してるのには違いなかろうが、そんな片鱗もぜーんぜん見せないところが素晴らしい。
ソロ・アーティストなのかバンドなのかもよくわからないが、全盛期にはバンド・メンバーもいないステージに一人で、軽薄そうな男が口パクのような歌を歌い飛び跳ねて踊ってるだけの能天気さ。
もちろん歌ってる姿を見たのはネット映像が普及したここ10年くらいの話で、それ以前の時代にはプラスティック・ベルトランがどういうライブを行うのか、そういう情報はなかった。
だから動いてる姿は近年になって知ったんだが、昔の映像とかいくつ見てもちゃんとしたライブっぽい姿は皆無なんだよね。 他に何か芸があるわけでもないだろうに、軽薄なぴょんぴょんダンスだけでメガヒットとは恐れいった。
曲調も簡単な3コードのロックンロールをひたすら単調なビートに乗せて歌うだけ、ただこの当時はロック的な歌には向かないと思われていたフランス語で見事にパンクをやっていたのが革新的と言えるのかな?
フランスではパンク初期の時代にメタル・アーバンやスティンキー・トイズなどのパンク・バンドがいたが、これらはいわゆるフレンチ風味はあまり感じられないものだった。
しかしベルギー=同じフランス語圏で生まれたこの曲はミッシェル・ポルナレフのようなフレンチ・ポップをパンクで再現したような軽薄・・じゃなかった軽快なエスプリの効いたもの。

日本盤が出た時は「恋のウー・イー・ウー」または「恋のパトカー」などという邦題がつけられていたな。
誰でもノリノリになれるハッピーさを持っていて、時代を超えて愛され続けるのもわかるよ。
有名無名に関わらずカヴァー曲の多さでもトップクラスだな。

その数あるカヴァーの中からROCKHURRAHがチョイスしたのがソニック・ユースによるもの。
プラスティック・ベルトランよりは遥かに知名度も高いと思われるが、1980年代初期から活動を続けているアメリカのバンドだ。
アメリカン・ロックなどと書くとROCKHURRAH世代ではどうでもいいバンドばかり思い浮かべてしまうが、実はノイズやアヴァンギャルド、オルタナティブなどのバンドの発生率も高い国なんだよね。
個人的にも大昔にはリディア・ランチやコントーションズ、ペル・ユビュとか聴き狂っていたもんな。
そういうノイジーなアプローチをしたロックの中で最も大成したのがソニック・ユースかも知れない。
個人的にはそこまでノイズという気はしないが。
ROCKHURRAHは彼らの全てを語れるほどにファンであった事はないけど、暴力的な混沌(ああ陳腐な言い方)を表現させたらピカイチのバンドだったね。
特にどんな曲をやっても見事にソニック・ユースっぽくなってしまう独特のギター奏法は数多くのギタリストに影響を与えたはず。
この「 Ca Plane Pour Moi」もまさにソニック・ユース調そのもので逆に何の飛躍もないけど、飛躍し過ぎて、このポップな原曲が途中で2回ほど眠くなってしまう16分もの壮大なノイズ組曲とかにならなくて良かった。
Teenage Kicks / Thee Headcoatees
2曲目も軽快なので行ってみよう。元歌はアイルランドの70年代パンク・バンドだったアンダートーンズのヒット曲だ。
ウチのブログでもちょくちょく名前が出てくるけど、大体いつも同じような事書いてるな。
反体制とかアナーキーとか過激とかのいわゆるパンクのステレオタイプなイメージとはかけ離れた、7:3分け長髪の70年代予備校生みたいなルックスの好青年がこのバンドの主役、フィアガル・シャーキーだ。
何だこの長いセンテンスとひどい文章?大丈夫か?ROCKHURRAH。
メンバーも普通にセーターとか着てて、ステージ映えがしないことこの上ないというバンドなんだが、一応ロールアップしたジーンズからDr.マーチンのチラ見せ、ダブルのライダースがパンク要素というわけか?
初期パンクの中にはこういう風采の上がらないタイプのバンドも多く含まれていて、バズコックスとかサブウェイ・セクトとか。
あまり「華」がなくても、ちゃんと名曲を仕上げれば世界的に著名になれるというところがパンクの魅力でもあったな。
アンダートーンズもモロにそのパターンで、50〜60年代ポップスなどの要素をうまく取り入れた軽快な曲を数多く残したバンドだった。
「Teenage Kicks」はその中でも最大のヒット曲で、多くの人に愛され続けた時代を超えた名曲のひとつだと言える。
初めて聴いた人は必ずその甲高い歌声にビックリするけど、このファルセット・ヴォイスも彼らの魅力。

この曲も色んなバンドがカヴァーしているけどグリーンデイだのアッシュだの、ワン・ダイレクションまでやってるのか?
どちらかと言うとヤンチャな若造バンド(最後のはバンドとは言えないな)がそれぞれの世代で何となくカヴァーしたものばかり。いくつ聴いても全然面白くもない駄作カヴァーだと思える。全く意外性がないんだよね。
しかも全然ウチのブログ向けじゃない。
上に書いたバンド達も本家アンダートーンズよりもずっと世界的にヒットした奴らなのに、この安易さ、このリスペクト感のなさは一体何?と嘆かわしくなってしまうよ。

そんな中でROCKHURRAHが許せる数少ないものがこのヘッドコーティスによるもの。
1970年代から90年代にミルクシェイクス、マイティ・シーザーズ、ヘッドコーツなどなど数多くのガレージ系、ブリティッシュ・ビート系のバンドで活躍したビリー・チャイルディッシュが仕掛け人となって手がけたガールズ・グループがヘッドコーティスだ。
彼女たちは演奏が出来るわけではなくて音楽の方はビリー・チャイルディッシュ達が担当、この4人は歌って踊るだけの添え物みたいなもんだが、ジャケット写真とかではちゃんと楽器持ってていかにもバンド風。
この辺の捏造もまた60年代っぽいのかもな。
とにかく「Teenage」というには無理がありそうな迫力のアネゴが投げやりに歌い、そして演奏はラウドなガレージ・ロックンロール。
好きな人にはたまりませんな、の世界だな。
ん、何とここまで長文書いて気付いたがこのヘッドコーティスは同じシリーズ「誰がCOVERやねん3+」でも書いてて、しかも前回もほとんど同じようなコメント書いてるな(笑)。
しかも元歌のアンダートーンズもこっちの記事で同じような書き方してるよ。アメージング。
自分の過去に書いた記事さえ覚えてないとは呆れるばかりだが、自分の書いた事が一応いつでも主義一貫しててメデタシ。
Isolation / Die Krupps
80年代初期のニュー・ウェイブが好きな人ならば誰でも、とは言わないがかなりの人が知ってるに違いない伝説的なバンドがジョイ・ディヴィジョンだろう。
ロンドン・パンクが誕生して間もない頃のマンチェスターでセックス・ピストルズが観客わずか数十人というライブを行った際に居合わせて、衝撃を受けた人物が何人もいたらしい。
後のバズコックス、マガジンのハワード・ディヴォートや後のスミスのモリッシー、そして後のジョイ・ディヴィジョンのイアン・カーティスなどがこの聴衆だったわけだが、彼らを中心にマンチェスターのニュー・ウェイブは花を開いてゆく。
パンクやニュー・ウェイブ初期の最重要レーベルのひとつ、ファクトリー・レーベルもここから生まれ、そしてジョイ・ディヴィジョンはそこの看板アーティストだった。
見たように書けばこういう感じでマンチェスター・ムーブメントは始まったんだろうけど、見てないROCKHURRAHはそこまで書けないのが悔しい。
とにかくジョイ・ディヴィジョンは音楽の流れがパンクからニュー・ウェイブに変換していった頃にファクトリー・レーベルから2枚の傑作アルバムを出し、インディーズ界のスーパースターとなってゆく。
が、度重なる癲癇の発作、鬱病、妻と愛人との三角関係などからイアン・カーティスは1980年に首吊り自殺をしてしまう。
自殺→レジェンドというのは個人的に好きじゃないからROCKHURRAHは今まであまりジョイ・ディヴィジョンの事を書いて来なかったが、彼らの作った音楽を愛しているのは今も変わらない。
彼らの最大のヒット曲は数多くのバンドがカヴァーしている「Love Will Tear Us Apart」だが、個人的に一番好きな彼らの曲は1stの1曲目「Disorder」、2番目に好きな曲が2ndの2曲目「Isolation」だ。
どちらもジョイ・ディヴィジョンの音楽を表すのにぴったりな単語をタイトルに用いているな。

その名曲「 Isolation」をカヴァーしたバンドは意外と少ないので少しビックリんこ。
有名どころではスマッシング・パンプキンズとこのデイ・クルップスくらいなのか?
スマパン、名前は知ってるけど特に興味ないからやはりROCKHURRAH的にはクルップスをチョイスするのが妥当だろう。
もう10年以上も延々とROCKHURRAH RECORDSでは語り続けていて、書いてる本人までもが「またか!」と思ってしまうが、ノイエ・ドイッチェ・ヴェレ(ドイツのニュー・ウェイブ)の中心バンドのひとつがデュッセルドルフ出身のデイ・クルップスなのだ。
D.A.F.によってノイエ・ドイッチェ・ヴェレの洗礼を受けた者が次に辿り着くのがデア・プランかこのバンド、というくらいに大御所なんだが、シュタロフォンという鉄パイプで自作した鉄琴のようなパーカッションを叩きまくって演奏するインダストリアル系バンドの真骨頂のようなのがクルップスだ。
エレクトロニクスを多用した音作りなんだが繊細でもクールでもなくて肉体派、工場労働系なのがまず良い。
自分が育った北九州も西の方は製鉄工場が盛んだったし、環境的には似てるからよりシンパシーを感じてるのかも知れないね。
ROCKHURRAHは福岡の80’sファクトリーというライブハウスで彼らの演奏している映像を見て以来、感銘を受けた人間なのだが、途中からなぜかメタル系の要素が見え隠れするようなバンドに変貌してしまい、ずっとファンで追い続けたというには程遠い関係。
最初の頃はとても良かったけどなあ。
最大のヒット曲「Wahre Arbeit Wahrer Lohn」を何度も何度もしつこいくらいに手直した音源を発表し続けたユーゲン・エングラーの愛すべき偏執狂ぶり、そういう愚かな部分を含めての魅力がこのバンドにはあった。

彼の押し殺したヴォーカルのスタイルとイアン・カーティスの歌声には一見共通するものがあるけど、エネルギーを放出し続けるようなクルップスと心の暗黒を内側に貯めこんでしまったイアン・カーティスは正反対、という気もするな。
もっと書くつもりでいたけど、意外と長くなってしまったので今日はこの辺でやめておこう。
まずは週末に頭を使う気力が起きるくらいまでは回復したいもんだ。
ではまた来週。Hasta luego(スペイン語で「またね」).